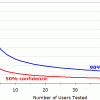オンラインアンケートは簡潔に
回答率を確実に高め、誤解の余地のある調査結果を出さないために、調査内容は簡潔にまとめて、わかりやすく答えやすい質問文を使おう。
顧客アンケートを作る際には、ある目的が他のどの目的よりも優先される。それは、回答率を最大にすることだ。回答率が低いと、その調査結果は大きな間違いの元になる。なぜなら、この結果は、大多数のユーザ(アンケートに答えるよりほかに、もっと大事な用がある)ではなく、もっとも熱心なユーザという偏ったサンプルにもとづいた結果になるはずだからだ。
調査から何が「わかる」かは問題ではない。全ユーザを代表していなければ、そのデータは信頼できないのだ。
どのようにしたら、平均的ユーザの回答を得られるだろうか。回答率が最大になるのは、アンケートが短時間で苦痛を伴わない場合だ。そして、アンケートを受ける時間と、それにともなう苦痛を減らす最良の方法は、設問の数を減らすことだ。
もちろん、アンケートの操作が簡単で、設問の内容とその選択肢がわかりやすいかどうかも、よく確認しておかなくてはならない。もし設問の内容を間違って解釈されたら、その回答は使えなくなる。インタラクティブなアンケートは、ユーザ・インターフェイスだということを忘れてはいけない。ユーザ調査にもとづいてデザインし、標準ユーザビリティ・ガイドラインに準拠するべきだ。(ペーパー・プロトタイプなら、午後いっぱいあれば、調査票の反復デザインが 3 回行える。)
アメリカ最大手の銀行 10 行のうちの 1 行が、最近、企業顧客を対象に 32 画面分の調査を行った。調査の内容も難しかった。多くの画面では、4 種類の企業向け銀行サービスを、6 つの側面からユーザに評価させていた。私たちの調査では、テストユーザは 3 画面で降参した。「私は小企業のオーナーだ。こんなことをやっている暇なんてない。」というのだ。(後で私自身、この調査を根気よく最後までやり通したが、おかげで、新しい著書のためのとんでもない画面ショットがいくつも収集できた。)
アンケート肥大化は、さまざまな分野からマーケティング責任者が寄り集まった当然の帰結だ。誰もがみんな、自分独自の関心事に対する顧客からのフィードバックを望んでいる。思い付く限りのすべての情報を集めようとする誘惑には、ぜひ抵抗していただきたい。何の情報も集まらない(あるいは偏った情報しか集まらない)のが関の山だ。
設問数を減らす
アンケート肥大化へのもっとも簡単な解決策は、設問数を減らすことだ。核となるニーズを満たす質問だけにしぼり、細かいことは省く。どのみち、アンケート調査は細かい違いを調べるのには向いていない。それには、直接観察が必要だ。
最近、Harvard Business Reviewに掲載された記事「The One Number You Need」では、顧客満足度に関する洞察のほとんどは、たったひとつの設問、すなわち「友人あるいは同僚に、[X] を推薦できる可能性はどのくらいですか?」への回答から得られるとしている。
14 件中、13 のケーススタディで、この 1 問が、長いアンケートと同等の顧客ロイヤリティ予測をはじき出していた。
自由裁量で使われるイントラネット・サービスでは、この質問を、「 [サービス X] を、同僚に推薦できる可能性はどのくらいですか?」に変えればよい。業務上必須のイントラネット・サービスでは、別の質問が必要だ。従業員たちは、たとえ問題のあるサービスでも、単にそれ以外の選択肢がないから「推薦」するかもしれないからだ。
分割して征服せよ
ふたつめの方法は、人によって質問を変えることだ。絶対に回答が必要な質問が 10 個あったとする。これを 2 問ずつに分けて 5 種類のアンケートを作り、1 画面に収まるようにする。各ユーザごとに、5 種類のアンケートからランダムにひとつを選んで提示する。
ウェブサイトはコンピュータなのだ。ソフトウェアを動かすその能力を活かして、ユーザごとに違うものを提示するのだ。(別の手段として、曜日ごとに違うアンケートを実施してもよい。ただ、曜日によってユーザに大きな違いがないことが前提だが。)
同じユーザに複数の質問をする必要があるのは、回帰分析や、その他の多変量解析を行いたい場合に限られる。しかし、私の経験上、ウェブ業界の人の大半は、多変量解析の話にはまったく何の反応も示さないので、実際に使うことはほとんどないだろう。
短いアンケートはよいアンケートだ。最後まで回答してくれる人の少ない(そもそも答える気になってくれればの話だが)肥大化したアンケートよりも、確実に良質なデータが集められる。
くわしくは
Frederick F. Reichheld: The One Number You Need to Grow. Harvard Business Review, 2003年12月, pp. 46-54.
2004年2月2日
記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。