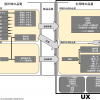ユニバーサルデザインとユーザビリティ
最近、ユニバーサルデザインという言葉を耳にすることが多くなった。強いて日本語に訳すなら普遍的設計ということになろうが、ようするに誰にとっても利用可能なデザインを目指していこうという動きである。この誰にとっても、という言葉の中には、従来のモノのデザインが、いわゆる「普通の人」だけを対象にしてきた、という反省が込められている。
ここで普通の人という言葉が使われているが、この普通という概念もいざ定義しようとしてみると、その曖昧さが明らかになる。そこには性別、年齢、職業、知識、経験、興味、などなど、さまざまな要因が絡んでいる。いったい普通の人というのが実際に存在するのかということになるのだが、あらためて考えてみればこれは一種の理想化であることがわかる。
知人のデザイナーであるアーロン・マーカス氏によると、一般のコンピュータやそのソフトウェアは、20代から30代の白人のホワイトカラーの男性を暗黙のうちに想定していることが多いという。これは何を意味しているのだろうか。容易に想像できることだが、それらはそのコンピュータやソフトウェアを開発している人たち自身の姿なのだ。
結局のところ、人間というのは何事に付け自分を基本に考えてしまいがちである。他人の立場にたって物事を考えるというのは、なかなか難しいことなのだ。その結果、作り上げられたコンピュータやソフトウェアは、開発者自身にとっては使い勝手は自明であり、機能的にも性能的にも彼らにとって優れたもの、ということになる。しかし、彼ら以外の人にとってはどうなのだろうか。そもそも、それらはどんな人たちを対象として想定して作られていたのだろうか。
こうした疑問は、ユーザビリティを基本概念とする国際規格ISO13407の中に表現されている人間中心設計という考え方によって解消される。この規格の中ではintended userという言い方をしているが、その表現の背後にある考え方は、各々の製品がどのようなユーザを想定して開発されているかがまず問題なのだ、ということである。
この考え方にしたがうと、不適切な製品が出てくる可能性は二種類あることになる。カテゴリー1の不適切な製品は、想定したユーザと実際に利用するユーザがずれている場合、特に、実際に利用するユーザを想定し忘れたり、し損ねていた場合である。前述のコンピュータやソフトウェアの設計者の誤りの多くはこのカテゴリーに属しているといって良いだろう。カテゴリー2の不適切な製品は、想定したユーザと実際に利用するユーザとの間にずれはないものの、そのユーザに関する正しい情報を得ていないために、ユーザの利用に耐えないものができてしまう場合である。
当然のことながら、カテゴリー1の製品をなくすためには、どのような人が使うのかをきちんと考えることが必要である。障害をもった人が使う可能性はあるのか、あるとすればその障害は、視覚障害、聴覚障害、身体障害、知能障害など、さまざまな障害のどれが該当するのか。障害というほどではないにしても、左利きの人は使うのかとか色盲の人は使うのかとか(これらは使わない製品を探すことの方が難しいだろう)ということも考えなければならない。
それ以外にも、高齢者の人が使う可能性があるとすれば、それは主に50代までなのか、60代なのか、70代あるいはそれ以上なのか。子どもが使うとすれば、それは中学生以上なのか、小学生も使うのか、それ以下の子どもも使うのか。外国人が使うとすれば、それはどのような民族の人たちなのか。また、いわゆるハイテク弱者(いい言葉ではないが)の人たちも使うのかどうかということも考えねばならない。特に、銀行のATMや駅の券売機のように、「誰もが」使えなければならない公共機器の場合には、かなり広範囲のユーザを想定しなければならない。
また、カテゴリー2の製品をなくすためには、該当するユーザの特性や生活の実態、要求のあり方などについて、正しい情報を得ることが必要である。そのためには、一般的ガイドラインを参照したり文献調査をすることはもちろんだが、質問紙調査によって必要なデータを新規に獲得すること、さらにできるだけ実際のユーザに接して面接や観察などを行うことが大切である。
このように、ユーザに対する適切な取り組み方をすべきであるという点において、ユニバーサルデザインの考え方は、ユーザビリティを扱う際の基本的な考え方と同じものである。なお、ユニバーサルデザインには、具体的な機器やシステムの実現に際して「共用品」という形態を考えるという側面もあるが、この点についてはまた別の機会に取り上げたい。
記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。