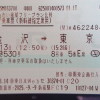ユーザビリティの究極の目標
私がユーザビリティを研究の目標とするようになったのは、個人的な理由が大きい。自分があまりしっかりした記憶力をもっておらず、また問題解決能力も高くないことから、結構いろいろな機器の操作で悩むことがあった。自分の性格が内罰的でなく外罰的であることから、その原因を自分の能力の低さに帰するのではなく、それは機器が悪いのだ、と考えるようになってしまった。だったら機器を使いやすく分かりやすくすればいい、というわけだ。同じようなことは建物の中を歩いていても感じることがあった。街を歩いていても感じることがあった。要するに迷子になったり、方位が分からなくなるのだ。これも同じことが理由だろう、と考えるようになった。意匠に凝って生活する人のことを考えない建築家に反発を抱くようになった。さらには、いろいろなシステムについても不満を抱くようになった。何で司法書士という人たちがいるんだ。それはシステムがわかりにくいからだろう。だったらシステムを分かりやすくすべきだ、というわけだ。こうした不満が累積し、それを人工物のユーザビリティというように概念化できるようになるには結構な時間を要した。
最近ではユーザビリティというキーワードがずいぶん普及してきたおかげで、問題はまだまだ山積しているものの、将来に対して明るい希望がもてるようになってきた。しかし、ここでまた疑問がわいてきた。果たしてユーザビリティの向上だけでいいのだろうか。ユーザビリティというのは究極の目標の第一歩にすぎないのではないだろうか。そんなことを考えるようになった。そんなとき、ニールセンのsystem acceptabilityという概念に出会った。またISO9126の利用品質の定義に出会った。そうだ、このようにしてユーザビリティの上位概念を考えて、その中におけるユーザビリティの位置づけを明確にする必要がある、と考えた。改めてそう考えると、ニールセンの定義するsystem acceptabilityも、ISO9126のquality in useの概念も、まだ途中段階のものに思えた。
そんなことを考えるようになったある日、アーロン・マーカスと話をしていてmeaningfulnessという概念に思い至った。うーん、一足飛びに究極の目標概念に到達してしまった感じがするが、これでいいのだろうか、と以後、ことあるごとに色々と考えてきた。クロスファイア研究会(crossfire@quickml.com)で、Shauna RiesとGenna MurphyのQuality of Lifeの本やPatrick W. JordanのHuman Factors in Product Designという本を読んだのも参考になった。
Quality of Life(以後QOLと略記)という概念は、北欧系の人々の好む概念で、それが生活の基盤になっているとされている。北欧系のHCI研究者は、この分野の研究もそこに目標を設定すべきだ、と主張している。そんなわけで、スウェーデンの知人に参考書を探してもらったのだが、どうも適当な本はないらしい。あまりに日常的な考え方なため、かえって本にはまとめられていない、ということらしい。そこでamazon.comで調べると、いろいろと検索できたのだが、どうもガン患者やエイズ患者などに対して、人間らしい生活を送らせるにはどうしたらいいか、というような類のものが多い。ようするに、これらは、日常水準よりも低下した生活を元の水準に近づける、という方向性のものである。前述の本は、そうした類書の中で、一般の人を対象にした数少ないものの一つであった。ただし、書いてあることは、臨床心理学(認知行動療法)の立場から、ストレスから解放された生活を送るにはどうしたらいいか、というような話が中心だった。そんなわけでユーザビリティとの関連性についてはあまり明確なヒントは得られなかった。
JordanにはDesigning Pleasurable Productsという著書もあるが、彼の考えを要約すると、モノはまず機能性があって初めて存在意義がでてくるもので、次にユーザビリティがあり、最後に楽しみ(pleasure)がくる、というものである。彼の考え方にはユーザビリティという概念が出てくるのでとても興味を持った。しかし、このpleasureという概念はたしかに重要なものではあるが、積極的な楽しみが無くとも「意味」があれば存在理由になるだろうし、彼が引用している感性工学の立場がpleasureという目標への解決策になるとも思えなかった。そんなわけで、Jordanの考え方には賛同しにくい部分があり、改めてmeaningfulという概念に舞い戻ってしまった私である。この概念の明確化についてはまた改めて書くことにしよう。
記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。