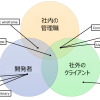発見的思考の獲得
発見というプロセスを成功させるには、チームに「未知の未知」を明らかにしようとするオープンさが求められる。発見の取り組みを、解決策ではなく問題に集中させよう。
発見は、何を構築すべきか、あるいはどのような方向性を目指すべきかを決めるのに役立つ。発見を適切に行うには、特定の思考様式、すなわち、発見的な思考と新しいことを学ぶオープンな姿勢を身につける必要がある。
解決策的な思考
発見のプロセスは、解決策の検討から始まってしまうことが多い。以下のような発見の目的について考えてみてほしい:
- AIチャットボットが、顧客の重要な質問にどのように答えるかを特定する。
- 新しいダッシュボードに、どのようなユーザーニーズがあるかを特定する。
- ユーザーが自分の注文を追跡できるフルフィルメント(訳注:注文・発送・配送など)トラッカーをどのようにデザインしたらよいかを探る。
これらの目的の問題点は、特定の解決策に過度に焦点を当てていることである。発見が解決策に焦点を当てて行われると、チームは調査を行う際に2つの一般的な認知バイアスに陥る可能性がある。
- アンカリング:解決策的な思考に陥っているチームは、特定の解決策の観点から発見型調査を行うことが多い。たとえば、問題がどのように発生し、誰にどのように影響を与えるのかといったその問題についての探索型調査を行うのではなく、プロトタイプをテストしたり、解決策についてターゲットユーザーにインタビューしたりするところから始めてしまう。
- 確証バイアス:採用したい解決策をチームであらかじめ想定していると、その解決策が正しいものであるという証拠を探しがちになる。その結果、問題や最適な解決策に対して自分たちが間違っていることを示唆する証拠を無視したり、そうした証拠をそもそも探そうとしなかったりする。
最初から解決策を念頭に置いて発見を始めてしまうと、ユーザーやユーザーニーズ、解決すべき問題に関する貴重な知見を発見する能力が限定されかねない。さらに、間違ったものを作り出してしまうリスクもある。

発見的思考には、新しい土地を探検する探検家のように、問題空間について新しいことを見いだそうとするオープンな姿勢が求められる。一方、解決策的思考は、顕微鏡で生物を観察する生物学者のようなものだ。
発見的思考とは
発見的思考とは、チームが以下のようなことを学ぶことにオープンであることを意味する:
- ユーザーの問題やニーズであれ、最適な解決策であれ、自分たちの想定が間違っていること。
- 自分たちが学べるとは思っていなかった新しいこと(いわゆる「未知の未知」)。「未知の未知」は、チームが問題領域について新しく重要な知識を得るにつれて、発見の方向性そのものを変えることもある。
発見的思考を採り入れることで、チームは貴重な知見を集めて、正しい問題と解決策を特定することができるようになる。
発見的思考を育むための3つの手法
好奇心を刺激し、早まった結論を避け、データ主導のアプローチを取り入れるために、発見の取り組みでは以下の3つの方策を活用しよう。
1. 目的自体をとらえ直す
発見を解決策的思考で始めてしまわないように、発見の目的の中心に、解決策ではなく問題を据えよう。
我々が開発するものはすべて、ユーザーの問題を解決するためのものだ。そうでなければ、それが使われることもないだろう。もし解決策をチームであらかじめ想定している場合は、その解決策でどのような問題を解決しようとしているのかを考える必要がある。
問いかけ:この解決策は、どのような問題を解決することを目的としているのか。
| 解決策 | 解決する問題の例 |
|---|---|
| ダッシュボード | ユーザーが最新のデータを使って適切な意思決定を行えるようにする |
| チャットボット | ユーザーに質問があるときに、安心感とサポートを提供する |
| 注文トラッカー | 注文がいつ届くかについての見通しを示し、ユーザーに安心感を与える |
問題を特定したら、それを発見の目的として位置づけよう。
たとえば、上記の問題に対して設定される目的は、以下のようになるかもしれない:
- ユーザーが適切な意思決定をできるように、必要なデータをどのように提供するかを決定する。
- アカウントに関する問い合わせをしてくるユーザーに、どのように安心感とサポートを提供するのが最適かを決定する。
- 注文の進捗状況をユーザーにどう明確に伝えるかを決定する。
問題を中心に据えた、より広範な目的から始めることで、回答が必要な重要な調査課題を特定しやすくなるはずだ。
たとえば、ユーザーが適切な意思決定を行うために必要なデータを提供することが目的である場合、ユーザーがどのような意思決定をしているのか、いつ最新のデータを必要としているのか、なぜそのタイミングで必要なのか、そして、意思決定プロセスにおいてどのようにデータを活用しているのか、といった点を調べる必要があるかもしれない。
2. 不明点と想定を洗い出す
発見的思考を身につけるためのもう1つの有効な方法は、自分たちが何を知っていて、何を知らないかに目を向けることである。発見の初期に、チームで時間をかけてこの作業に取り組むことで、自分たちの想定を正しいと証明しようとする考えに陥りにくくなるからだ。
チームで、事実、想定、不明点を洗い出そう。これは、キックオフワークショップの中のアクティビティとして実施できる。
問いかけ:ユーザーのニーズや行動、あるいは問題のコンテキストについて、我々はどのような想定をしているだろうか。
さらに、チームで不明点や想定に優先順位をつけるとよい。不明点の中には、放置すると大きなリスクを負うことになり、対応が不可欠なものもあれば、知っておくとよいが、プロジェクトの成否には関係しないものもある。
3. お気に入りのアイデアをクーラーボックスに入れる
チームが特定の解決策に固執するのを避けるために、発見の初期に解決策のアイデア出しを行い、調査が終わるまではそれらのアイデアを「凍結」することに合意しておくとよい。この作業は、発見の目的や調査課題を設定する前に行うキックオフワークショップの中で実施することができる。
問いかけ:今、どのような解決策のアイデアがあるだろうか。それらを記録して、後で検討できるように保管しておこう。
解決策のアイデアをクーラーボックスに入れておくことには、2つの利点がある:
- 特定の解決策に思い入れのあるメンバーにとっては、自分のアイデアが聞き入れられ、きちんと記録されることで、それがなかったものにされる心配から解放される。
- チームがひとつの解決策だけを念頭に置いていたとしても、他のアイデアを検討する余地が生まれ、視野が狭まるのを回避できる。
チームが発見型調査を終え、その結果をもとにアイデア出しを始める段階になったら、クーラーボックスに入れておいた解決策を見直し、適切なものがないかを検討すればよい。
結論
発見を成功させるには、正しい思考法、つまりオープンで特定の解決策にとらわれない姿勢が求められる。そのためには、解決策ではなく、問題を中心に発見の目的を設定し、初期段階では解決策のアイデアをすべて洗い出してクーラーボックスに保管し、検討が必要な想定や不明点を特定することに時間を費やすべきである。
記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。