オフィス家具から文具まで——人の多様性を起点に考える、コクヨのインクルーシブデザイン
毎年恒例、HCD-Net認定人間中心設計専門家・スペシャリスト認定者へのインタビュー。2025年は、コクヨ株式会社のデザインエキスパート、藤木武史さんにお話を伺いました。
藤木武史さんはコクヨ株式会社ステーショナリー事業本部のCX(カスタマーエクスペリエンス)デザイン部署に所属し、デザインエキスパートとして活動しています。プロダクト(工業)デザイナーとして製品開発に関わるなかで、どのように人間中心設計(Human Centered Design、以下HCD)の考えに至ったのか、事例を伺いました。

藤木さんは新卒でコクヨに入社して以来、プロダクトデザイナーとしてキャリアを積んできました。入社当時は海外や首都圏向けのオフィス家具を担当し、その後入社時からやりたかった文房具部門へ異動。空間を占める割合の大きな製品から、手のひらに乗るような細かい製品のデザインまで、幅広く手がけてきました。
CXデザイン部署では、実店舗での購買行動を継続的に観察・リサーチして商品開発へ反映しています。近年は自ら手を動かすよりも、ブランドやデザイン方針を定めるディレクション業務を中心に担っています。「KOKUYO ME」ブランドの立ち上げや、高級筆記具のディレクションなどを推進してきました。社外では、2020年にNPO法人「インクルーシブデザインネットワーク」を立ち上げ、専務理事として運営に携わっています。障害のある方や学生と共創し、観察から試作、検証の流れを実地で回すこの活動は、社内の実務にも活かされているといいます。
観察することで価格競争と異なる観点で差別化する
藤木さんがインクルーシブデザインやHCDを意識するようになったのは、オフィス家具に関わっていた時代に手がけたロビーチェアの開発だったといいます。きっかけは官公庁向けの入札案件でした。価格競争が激しいなか、利用実態に根差したストーリーと仕様で差別化したいという狙いがありました。
当時の社内ではユニバーサルデザインの流れが文具中心に進んでおり、家具でも同様の考え方を取り込む方針が示されました。藤木さんと現場のデザインチームは「ユーザーを招いて実際に使ってもらい、観察する」というプロセスを提案しました。

ユニバーサルデザインの専門家の助言を得て、妊婦さん、車いすユーザー、盲導犬ユーザー、杖ユーザーなど、5名ほどの多様な当事者の方々がリクルーティングされました。調査のために、カタログ撮影を行うための社内のスタジオに既存の椅子やカウンターなどを持ち込み、市役所の窓口環境を模した仮設市役所を再現したといいます。参加者には実際の庁舎であるような「椅子を引く」「机を出す」などの動作をお願いし、その後撮影した写真を見せながらヒアリングを行いました。
観察の結果、「背もたれに体を預けない“ちょい掛け”行動」が一定数あることがわかりました。これにより「背もたれのない短時間用の椅子」「手すりを小さくして座面を広くする」「妊婦さんが立ちやすい浅い座面」「盲導犬が足元で休めるスペース」などのアイデアが生まれました。さらに、車いすの待機位置を前方に確保できるよう、椅子の寸法を見直し、空間レイアウトにも連動する約5項目への「デザインコード」へと整理しました。
調査はいくつかのサイクルで回され、現場での検証として実際の市役所にプロトタイプを一日設置し、来庁者の利用も観察することで、混雑・視線・音による影響も確認しました。
関係者を巻き込み、販売までデザインしなければ成功はない
最初の1回はデザイナーだけで調査を行っていましたが、その後の調査には設計士や空間設計のチーム、営業担当も同席する体制に変更したといいます。体制変更の背景には、藤木さん自身が営業の責任者を務めた時期があり、「売るのは大変だ」と苦労した経験がありました。
「プロジェクトを成功させるためには、販売するところまでデザインをしなければ成功しないと思ったんです。彼らは彼らで悩みが結構多い仕事なので、ご自身の役にも立つだろうと参加してくれました。」と藤木さんは語ります。
設計士や空間設計の担当者も、「理屈がある設計」を行うためには一つの指標になるということで参画してくれたといいます。

何度かの調査の結果をもとに、コンセプト合意と投資判断のため、入札仕様書を想定した「仮想カタログ」が作成されました。デザインコンセプト、製品説明、利用者にもたらす効果までを可視化し、経営層へのプレゼンを実施しました。プレゼンの反応は高評価で、観察プロセスを伴う仕様提案で官公庁入札での採用率が高まり、製品は今も長く愛用されているといいます。
このロビーチェアでの成功後、社内では手法の横展開を狙い、「ユーザーの観察と分析に特化した“観察プロジェクト”」を立ち上げました。プロダクト個別の開発から切り離してシステマティックにやり遂げる仕組み化を試みましたが、コストと成果のバランスにより「なかなかシステムにならなかった」と藤木さんは語ります。その後プロセスの採用は減少していきました。
製品のデザインに再び観察を取り込み、「切りやすい」を定量化
プロセスの適用が少なくなった後も、藤木さんは社外では2020年にNPO「インクルーシブデザインネットワーク」を設立し、専務理事として活動をはじめました。「若い人や障害当事者とともに、当事者の気づきを起点に課題を見出し、デザイナーが解決策を形にする」年次ワークショップを実施し、手法を毎年ブラッシュアップしていました。
近年、インクルーシブデザインをもう一度本格的に進める動きが社内で起こったことを受け、過去の取り組みをもう一度やろうと、再び製品開発にユーザー観察のプロセスを取り入れるようになりました。その代表例が、右手・左手の別なく使いやすいハサミ「サクサ」です。社内の技術者が提案した「刃を傾斜させると切れ味が変わるのでは」という仮説に着目し、複数の試作品を用いた行動観察と評価で仕様を詰めていきました。

まず、上肢障害のある当事者の方々に協力を依頼し、試作で切断テストを実施しました。量産時のばらつきの影響も考慮し、約600個を成形して条件の揃った試作品を約10点抽出。左利きや上肢障害の参加者を含め再検証し、8種類の持ち手で刃角度の違いによる切断性を比較しました。試作品と合わせて、市販の100円ハサミ、海外製品などとも比較を行ったといいます。切る対象には、サランラップといった柔らかいものから、段ボールやカーペットなど日常で切りづらいものを中心に設定しました。しかし、調査に差が出なかったと藤木さんは振り返ります。

「他社の製品でも試しましたが、データに差が出ませんでした。絶対におかしいなと思ったんです。そんなわけがないと思って実験をすると、最初のデータだけちゃんと差が出て、2回目のデータは取れなかったんです。」
観察を重ねるうちに、人は1回目に切れないと2回目から無意識に調整してしまうため差が消えてしまうことに気づいたといいます。「評価に使えるのは一裁ち目だけ」という前提が明らかになったため、調査の設計を組み直しました。母集団を拡張するため、大学の学生に参加を依頼し、最初の一裁ちに限定した比較実験を集中的に行いました。結果、ある角度で成型したものの切断確率が一気に上がるということが明らかになり、量産に向けた意思決定の根拠となりました。
製品だけでなく、並行してパッケージも検証しました。環境負荷の観点からプラスチックから紙パッケージへ切り替え、視覚障害者向けに音声でスペック・使い方を案内する「アクセシブルコード」を採用しました。大学の購買部と協働で購買行動の観察実験を行い、ユーザーが何に注目して商品を選ぶのかを分析しました。

「製品の結果が出るのには時間がかかるんです。その商品が売れているかどうかをこれから問われるわけです。講演などで褒められても、気持ちはドキドキしています。」と、プロセスと成果への関係を藤木さんは冷静に語ります。
多様なユーザーがともにデザインする拠点をつくる
藤木さんは、多様な人と共創するための実験場として、2023年に共創拠点「HOWS PARK(ハウズパーク)」を立ち上げました。コクヨの特例子会社「コクヨKハート」に所属する障害のある社員と一緒に、文房具や家具の開発を行っています。
活動の基本は、HCDのプロセスそのものだといいます。まず「観察」で課題を見つけ、次に「洞察」と「試作」を経て、「検証」で改善点を見つける。この一連のサイクルを、障害当事者とデザイナーが一緒に回していく仕組みを整えました。
象徴的な成果が「片手で開けられるバインダー」です。上肢に障害のある社員の「バインダーを片手で開け閉めできない」という声から始まり、開き方の仕組みや指をかける部分の形状を試作・検証しながら改善を重ねました。
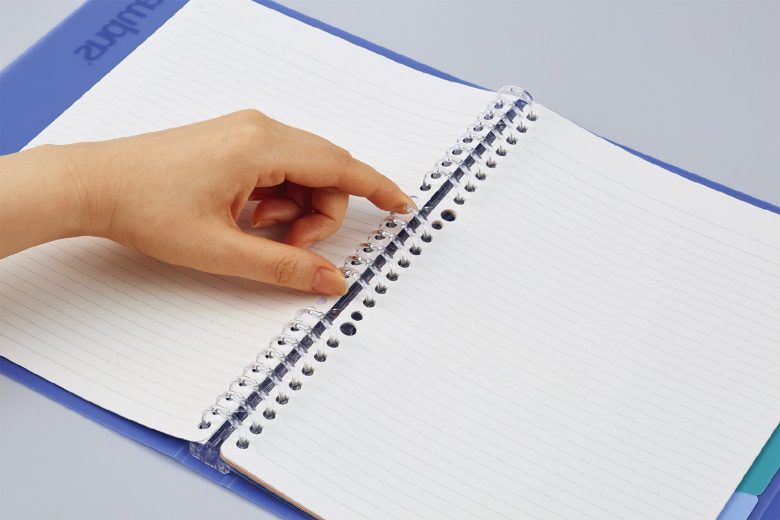
もうひとつは、発達障害や色覚特性のある学生とのワークショップから生まれた「青い暗記シート」です。従来の赤・緑の組み合わせでは見えづらい人がいることを知り、視認性と集中しやすさを両立する青系に変更しました。結果的に一般ユーザーからも「目が疲れにくい」と高評価を得ています。
こうした活動を社内に浸透させるために、「HOWS DESIGNマーク」をつくり、当事者と共創したプロダクトに認証を与える制度を始めました。多様な人々と共に課題を発見し、解決のプロセスを経て生まれたものを可視化することで、人間中心設計を企業文化として根づかせる狙いがあるといいます。
経験値だけではなく、実践を言語化し整理するのが認定資格
人間中心設計の資格との出会いは、藤木さんが講演でロビーチェアの事例を発表したことからでした。資格保持者だった聴講者に「あなたのやっていることはまさにHCDですよ」と声をかけられたのがきっかけだといいます。
他の業界に比べてデザインの分野には公的機関の資格が少ないと思っていたこともあり「これまで経験値だけでやってきたことを理論として整理したい」と資格を受験しました。受験時にはコンピタンス項目を壁一面に貼り、自分のプロジェクト経験を照らし合わせながら整理したといいます。これによって観察・分析・設計・評価の流れが理論的に理解できるようになりました。「プロトタイプ評価は自分たちにとって大きい活動ですが、コンピタンス上は1つにすぎません。調査設計などの複数の視点が組み合わさって初めて成果が成立するという理屈を理解できました」と藤木さん。「実践を言語化できたことが最大の収穫」と語ります。
資格を取得したことで、専門領域を明確にできたことも大きな効果だと感じています。藤木さんは「この資格はキャリアアップのためというより、経験を理論に結びつけて、社会に信頼される専門家としての姿勢を示すものです。資格を受けるために自分で勉強し、過去の経験を整理するプロセス自体が、仕事をする上で必要なことだと思います。自らをステップアップするための一つの機会にしてほしい」と語ります。

藤木さんのデザイン活動には、家具から文具へと領域が変わっても一貫して「実態を見て設計へ落とし込む」姿勢が根幹にあります。藤木さんは、工業デザインとHCDの間にはまだ一定の距離があるとしつつも、工業系デザイナーにとっても「ジャンプアップできるチャンス」と締めくくりました。現在、コクヨにおけるインクルーシブデザイン推進のリーダーの一人として、社内外のネットワークを活かしながら活動を広げています。
藤木さんは、今後の目標を「プロセスでの商品が事業としても成果を出すこと、そして今度こそ、多様性がある社会の実現を目指してデザインの力とHCDから学んだ知見で日常に浸透させていくことです。」と語ります。
※文中に記載されている所属・肩書は、取材当時のものです。
人間中心設計専門家・スペシャリスト認定試験
あなたも「人間中心設計専門家」「人間中心設計スペシャリスト」にチャレンジしてみませんか?
人間中心設計推進機構(HCD-Net)の「人間中心設計専門家」「人間中心設計スペシャリスト」は、これまで約2500人が認定をされています。ユーザーエクスペリエンス(UX)や人間中心設計、サービスデザイン、デザイン思考に関わる資格です。
人間中心設計(HCD)専門家・スペシャリスト 資格認定制度
- 受験申込
- 2025年11月4日(火)~2025年11月25日(火)16:59締切
- 主催
- 特定非営利活動法人 人間中心設計機構(HCD-Net)
- 応募要領
- https://www.hcdnet.org/certified/apply/apply.html
人間中心設計推進機構のサイトへ移動します
記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。




