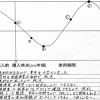ユーザビリティの研究と実践
ユーザビリティに関する研究というと方法論の開発が中心になるだろう。歴史的に見ると、設計の方法論(UIMSなど)、評価の方法論、プロセス管理の方法論、そしてユーザリサーチの方法論というように展開してきたように思う。設計ノウハウを外化してガイドラインの形に整備するという研究もあるが、多くの場合、そのガイドラインは評価や設計手法に組み込まれることが多く、その意味では方法論開発というカテゴリーに含めることができるだろう。
こうした方法論の開発は現場の企業で行われることもある。たとえばHoltzblattがContextual Inquiryの手法を開発したのは彼女がDECにいたときだった。しかし手法に関する研究の多くは大学などの研究者によって行われてきたし、現在でもそうした傾向が強い。特に評価に関する研究は現在でもそうした人々によって活発に研究されている。しかし、日本でも欧米でも、企業の現場にいるユーザビリティエンジニアに話を聞くと、特にモデル的な手法については「研究としては面白いが、実際には使えない。ユーザビリティテストで十分だし、それが一番効果的だと思う」といった意見がしばしば返ってくる。これはどういうことだろうか。
評価に関して考えると、まずその活動はformative evaluationとsummative evaluationに区別される。後者はCIFを利用するような場合に必要になるが、現場で行われている評価の大半は前者であるといっていいだろう。要するに評価の結果は、設計者やデザイナに問題点をフィードバックするという目的に使われているのだ。その目的の場合、評価結果に求められるのは、(1) 信頼性と妥当性が高いこと、(2) 効率的であること、(3) わかりやすいこと、(4) インパクトがあること、あたりだろう。
こうした点で、ユーザビリティテストは、一般にサンプル数が少ないことから信頼性や妥当性については疑問視されることがありうる。実際、テストの結果をレポートにまとめても、得られた結果がどの程度一般化できるのかについて設計者やデザイナに疑いを持たれる、ということがしばしば発生した。また効率性という点でも、特にプロトコル解析の技術をそのまま適用していた初期のころは、日数のかかるテストに対して使いものにならないという批判がなされていた。しかし、結果が分かりやすいという点ではユーザビリティテストに優るものはないだろう。結果の分かりやすさという点では数値化することを望む声も多かったが、テスト結果をCIFのように定量化することも可能である。ここに書いたようにすべての点で優位な手法ではないにもかかわらず、ユーザビリティテストは今や評価の定番となっている。その一番の理由はインパクト性にあるのではないか。ユーザが困惑している現場を目の当たりにすることは、設計者やデザイナにとって「これは何とかしなければ」と思わせるに十分である。
インスペクション法は、ユーザビリティテストの効率性の低さについて特に焦点を当てたものだが、評価担当者の主観ではないのか、という「疑念」が残り、インパクト性という点で今一つである。また効率性についても、ユーザビリティテストでは、近年はパソコンを利用したログツールが頻繁に利用されるようになり、以前に比べれば大分改善されてきた。そのようなわけで、インスペクション法は、特にその簡便さが注目され、現在でも良く利用されているが、ユーザビリティテストに取って代わる手法とまではなっていない。
さて、こうした中で、大学や研究所で良く取り上げられているモデル的な手法はどうだろう。ロジックが明確であるため信頼性は高いといって良いだろうが、まず現場的に見ると妥当性について疑問をはさむ余地がある。モデル的アプローチでは、パラメータとして取り上げたものが本当にそれだけなのか、他にも可能性は無いのか、といった点が気になる。もちろんモデルというのは基本的なロジックを外化する点に特徴があるので、やたらにパラメータを増やせばいいというものではない。またロジックそのものに、人間の行動を外化しているという意義があるので、研究者が人間やタスクをどのように見ているかを整理した形で提示することができる。しかし、ともかく現場では対象となる機器やシステムで本当に問題となっている点を見つけだすことが重要である。パラメータによって説明された事実が、実際のユーザの行動をちゃんと表現しているのか、といった点が現場の担当者としては気になるところだろう。この点で、論理を重視する研究アプローチと、有用性を重視する現場的アプローチの間には乖離があるといえる。
また、複数の仕様案があったときに、そのどちらが効率的に作業できるのかを考えたり、ある仕様にしたがった作業のどの部分にネックがあるのかを見つけるために、モデル的な手法は有用な示唆を与える。しかし、現在のユーザビリティ活動では、user experienceという言い方もあるように、単にテーラー主義的な作業効率という観点だけでユーザビリティを評価してはいない。ユーザが主観的に満足しながら仕事ができるかどうかも大切なポイントである。その意味では、そうした主観的側面をも考慮にいれたモデル的アプローチがでてくれば、現在のユーザビリティ工学の流れにも対応し、広く受け入れられる可能性があるだろう。
さらに、モデル的な手法は、効率という点でユーザビリティテストより有利だろう。特に最近ではコンピュータを利用して、自動的にモデルの計算を行うことができるので、時間的には短時間のうちに結果が得られるはずである。また結果は定量的に示されることが多いので、わかりやすさという点でもメリットがある。またインパクトという点でも、ユーザ行動をまのあたりにすることに比べると多少劣るかもしれないが、結果に大きな差がでてくれば、関係者にとっては明瞭な印象を与えることができるだろう。このようにモデル的な手法は単に研究者の机上の空論ではなく、現場的にも活用できる可能性を秘めているのだ。
評価の方法論を例にとりあげて、ユーザビリティの研究と実践の関係を考えてきたが、評価手法、特にモデル的な手法を研究する際には、それが実践の現場で使えるようにすることが重要である。そのためには、妥当性を高めることと、主観的満足度を含めたユーザの全体的行動を扱うようにすることが必要ではないかと考えられる。いいかえれば、評価手法のユーザであるユーザビリティ関係者が、ユーザビリティ活動の実践の現場でどのような問題に悩み苦労しているかを知ること、そうしたメタなユーザ工学的態度がモデル的アプローチに代表されるユーザビリティ研究に必要とされるのだ。
記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。