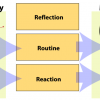内観を大切にしよう
ほんとうに欲しいのは行動の結果ではなく、その意味である。ユーザビリティ関係者にしてもマーケティング関係者にしても、もちろん心理学者にしても、事実だけにこだわる行動主義の限界を感じていた。意味を考えるために、行動主義の規範から外に踏み出してしまっているのであれば、解釈に影響を及ぼしている担当者自身の内的プロセスに対する内省や内観をもっと重視すべきである。
内観(introspection)というのは、自分で自分の気持ちや考えを内省することで、どのような時にどのような気持ちや考え方になるか、どうしてその考え方がおき、行動をしたのか、これからどのようなことをしたいのか、などを考える方法である。
ごく初期の心理学ではこの内観法が良く用いられていたが、内観法によって得られた情報は、それが事実であるか、というか、そのとおりのことであるのかどうかを確認することができず、内観そのものは適切であっても、それを報告した場合に、そこに虚偽や歪曲が入ってしまう可能性を排除できない。
このことを敷衍すると、たとえば、この製品が好きですと言う反応を得ても、それがお世辞なのか本心なのかは区別が困難だし、何が欲しいかと聞かれた時の回答についても、それがたまたまそのときに頭に浮かんできたことなのか、それともずっと以前から欲しいと思っていたものなのかは区別することが難しい。さらには聞き手との人間関係によって、たとえば謝礼を幾らくれるのだろうとか、聞き方が気に入らないとかいったことによる影響を排除することはできない。要するに、内観にもとづく反応には信頼性が低いという面がある。こうしたことから、内観にもとづく心理学は、行動主義(behaviorism)心理学によって批判された。
その行動主義では、客観的事実しか扱わないことによって心理学を科学として水準の高いものにしようと考え、たとえば鳩がレバーをつつく反応とか、ネズミが迷路を走る所要時間のような客観的データにこだわった。ユーザビリティに関連していえば、同じことをするのに幾つかの手段があった時、ある製品を選ぶ頻度が他の製品に比べて高いかどうかといった計数値を用いる方法に対応する。また生理的な反応や身体的反応は嘘をつかないと考えられ、マーケティングでも脳波計測や眼球運動の計測が利用された。
しかし、それだけでは関係者の欲しい情報は得られない。ユーザビリティ関係者にしてもマーケティング関係者にしても、もちろん心理学者にしても、事実だけにこだわる行動主義の限界を感じていた。なぜなら、ほんとうに欲しいのは行動の結果ではなく、その意味だからだ。ある製品が高い売り上げを示したといっても、それは店頭にその製品しか並んでいなかったからかもしれないし、単に取りやすい場所に陳列してあったためかもしれない。またその製品を手に取ったとしても、それをいいと思って取ったのか、特に意味もなく取ったのかは分からない。そうしたことも重要だが、ほんとうにその製品が良かったかどうかをきちんと把握することはできない。これではマーケティング的な解釈や予測は困難である。さらに言えば、そうした形で厳密な科学になることにどういう意味があるのか、という反省もあった。
そうしたことで我々は評定尺度とかアンケートとかインタビューといった手法を採用するようになった。それによって、そのユーザの行動の意図と一応考えられる情報を得ることができるようになり、それなりにユーザの行動モデルもたてられ、また予測もできるようになった。
さて、そうしたユーザの回答が産まれてくるプロセスを考えてみよう。まず、考え方や意志、動機付けといった内的状態とその変化がある。次にそれを当人がどのように認知するかという問題がある。この段階でまず様々なバイアスが影響してくる可能性がある。内的状態は同一でも、たとえばそれを自分の本当の気持ちととらえる場合もあるだろうが、それに疑念を抱いている場合もある。さらにその状態に対する因果的な推論をした場合には、その原因となったことについて内省した時に、たまたまその時に浮かんだことを原因なり影響要因と考えてしまうことは大いにありうる。
次に、そうした自己分析や自己認識を尺度の評価値や言葉に変換するプロセスで第二段階のバイアスがかかってくる。評価値の変動については順応水準の理論などが知られているし、言葉に変換する場合には、言語体系、たとえば何語で考え、それを言語化するかによって強いバイアスがかかってくる。これらは次のように表現されるだろう。
| 内的状態 | → | 内的状態の認知 (第一のバイアスの可能性) |
→ | 認知結果の言語報告 (第二のバイアスの可能性) |
我々はアンケート調査やインタビュー調査を実施して、それが「他人から得られた」情報だからといって素直に信頼してしまう傾向があるが、こうした二段階の歪曲プロセスが存在する可能性を考えると、素直にそれを信じてしまうことに疑問を持つべきだ、ということになる。こうしたバイアスをチェックするために、心理テストなどでは虚偽尺度というものを使ってその信頼度をチェックすることがあるが、それが最適なチェックになっているかについては疑問があるし、また絶対的なものだとも言えない。
ちなみに先の図は、ユーザサイドにおけるバイアスの存在を示していたが、担当者におけるバイアスもありうる。
| (認知結果の言語報告) | → | 言語報告の解釈 (第三のバイアスの可能性) |
→ | 解釈結果の報告(言語化) (第四のバイアスの可能性) |
ただし、あまり懐疑的になってしまうと何もできなくなってしまう。そこで、我々はそれなりにアンケート調査やインタビュー調査を実施し、その結果を解釈して消費者やユーザの行動の意味をとらえたものと考えている。
しかし、そうした結果を即物的にとらえてしまい、できるだけ推論や憶測を交えないようにしようとするマーケティング担当者やユーザビリティ担当者はたぶん少数だろう。実際には、得られた情報、たとえそれが数値化されていようと、言語的データであろうと、それを解釈する担当者の認識プロセスが重要であることについて、異論はないだろう。ようするに担当者は得られたデータの意味を解釈し、できるだけ客観性を担保しながら、その分析を行っているのだ。
実は、その解釈をする主体の認識プロセスを考えてみると、これは解釈をする人にしか分からない内的なプロセスである。そう、解釈をするということは、解釈をする担当者の内的プロセスなしには成立しない活動なのである。そして、その解釈に対して、担当者は常に反省をし、その適切さを考えているだろう。その反省がどの程度の水準かによって、担当者の能力の上下が決まるといってもいい。
ということは、担当者自身の内的プロセスが、他人から得られた情報の解釈にも強く作用しているということである。さらにいえば、他人から得られた情報だけを扱っているのが適切といえるだろうかという重要な疑念にたどりつく。たしかに回答者は一般に複数であり、それだけにデータの信頼性は自分自身の個人的判断だけに基づく場合より高いといえる。しかし数だけが問題なのではない。我々はすでに意味を考えるために行動主義の規範から外に踏み出してしまっているのだ。であれば、そうした解釈に影響を及ぼしている担当者自身の内的プロセスに対する内省や内観をもっと重視すべきである。いいかえれば第三のバイアスを恐れることなく、果敢に積極的に自分の洞察力を駆使して内観的解釈を行うべきなのだ。
自分自身の内観は、自分の心的プロセスに影響している要因をどの程度自覚できているかによって、その価値が変動するが、それなりに自分の判断の偏り具合や、自分の洞察力の深さを認識することができていれば、まだ言語的あるいは数値的な外化を経ていないだけに、第一段階のバイアスだけしか影響していないことになる。つまり、他人から得られた情報よりも信頼度が高いといえる。
こうしたことを考えると、表面的な客観性を重視するあまり、やたら他人から情報を得ようとしてアンケートやインタビューをする前に、まず自分の頭のなかで、じっくりと仮説を構築し、いろいろな可能性を考慮し、自分だったらどのように考え、判断し、行動するかを考えてみることが必要だといえる。さらにいえば、そうした内面的で自省的な能力をどの程度もっているかが、有能なマーケティング担当者やユーザビリティ担当者といえるかどうかを決定するといえる。
特に、UXを問題にした場合、経験といっているものは、経験に対する評価のことであり、ユーザの内的プロセスが強く関係している。そのため、UXの研究や調査をする場合には、自分の内的プロセスの特徴をきちんと把握し、かつ深くて強い洞察力をもっていることが必要になる。
くりかえすことになるが、他人から得られたデータをいじくっているだけでは、有能な担当者とはいえない。自分自身に関する内観や洞察をきちんと行い、それにもとづいて得られた情報に意味づけを行っていくような担当者が必要なのである。
記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。