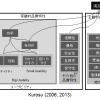幻の満足を得たい気持ち
人々はユーザビリティの低い製品を買ったとき、なぜそのことに文句を言わないのかが不思議だった。もちろん文句を言う人もいるし、時にはクレーマと呼ばれる程の強硬な態度を取る人もいる。もちろん釣り銭が足りなかったり、野菜が腐っていたり、買ったばかりのテレビが故障したりすれば、店に文句を言うのが普通だろう。ところが使いにくいとか操作がわかりにくいという理由で店に文句を言ったり、メーカーの電話窓口に文句を言う人は少ない。
それで、日本のユーザは内罰的なのではないか、という仮説を提示してきた。フラストレーション事態に対する反応の仕方は性格によって異なり、自分に原因があるとして自分を責める内罰型、相手に原因があるとして相手を責める外罰型、誰に原因があるのでもないとして特に誰も責めない無罰型、といったタイプが区別されている。たしかにアメリカのような国と比較すると日本のユーザは大人しい。その原因を、彼らが、自分にはそれを使いこなす能力がないのだからと諦めてしまったり、買ってしまったのは自分なんだからまあ仕方ないかと思ってしまったりする傾向があるのではないかと考えていた。
たしかにそうした傾向があるようには思う。しかし、もう少し考えてみると、不快感の表明の強さは対象への関与度の強さに関係しているように思える。自分が本当に必要としているものだったら、もしそれがうまく動かなかったり、うまく扱えなかったりしたら、本当に困る筈だ。本当に困った時、人は完全な冷静さを保つことは難しいだろう。不快を感じ、それを表明するだろう。
たとえば水洗トイレの水が流れなくなったら、たとえば冷蔵庫が故障したら人々は慌てるだろう。それは、そうしたモノが本当に生活に必要だからだ。しかし電子辞書が故障しても人々はそれほど慌てない。なぜなら、電子辞書がなくても紙の辞書があるし、もしそれがなければちょっと本屋に行けば良いし、あるいはインターネットの辞書機能を使うことも出来るからだ。現代の生活は冗長にできているし、フェイルセイフができているからだ。
こうした生活環境の中、本当に「それがなければ」困るモノ、生きてゆくのが困難になるものというのは数少ないだろう。いいかえれば、人々の生活の中にある人工物の大半は無くてもやっていけるもの、あるいは代替品があるものなのだ。
それでは我々の身の回りにあるものの大半がなくてもいいものだとしたら、なぜ我々はそれらを買って身の回りに置くのだろう。実際、身の回りには使っていないものがかなりある。1年以上さわったことのないものがあれば捨てるべきだ、と言われたことがある。それよりも部屋のスペースの方が大切だというのがその人の主張だった。しかし、それをなかなか実践できずにいる。なぜだろう。たぶん、無くてもいいものたちが無くなることによって生活が貧しくなるような気がするからだろう。
何となくあった方がいい。何となく「それら」があることによって生活が豊かであるような気がする。これは現代のマーケティングの基本戦略だろう。そして私を含めた多くの人々が豊かさを目指す戦略に乗せられている。しかし、「それら」があることによる満足感はそれほど実体のあるものではない、と多くの人が薄々は感じているのだろう。その故に、本当に必要でないものに対してはユーザビリティが低かろうと大きな問題ではないと考えているのではないだろうか。人々がユーザビリティより切実に感じている信頼性だって、場合によると問題にされないことがある。あまり使っていないもの、あまり必要性を感じていないものが壊れたとしても、修理にださず、そのまま捨ててしまうことがある。使わずにいて結局捨ててしまうのであれば、それは無かったも同然である。
様々な機器に囲まれた生活、より一般的にいえば多様な人工物に囲まれた生活は、それが少ない生活に比べて豊かで満足できるもののように思えるのではないだろうか。そうした形で満足感を得たいという気持ちから、人々は本当の必要性について顧慮することなく、いろいろな機器を購入してしまっているのではないだろうか。ユーザビリティに対する一般ユーザの態度を考えていると、そんなことが考えられてくる。
記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。