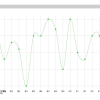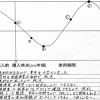質的データの分析に手法は必要か【更新】
いろいろな分析法を利用することは、時にマネージャや設計者、デザイナなどの関係者が頑迷な場合には理論武装として必要だったかもしれない。しかし現在においては、もう必要ないのではないか。
近年、エスノグラフィックなアプローチが注目されるようになり、同時にそこから得られたデータの分析法として様々なものに関心が寄せられている。ユーザビリティ関係者やUX関係者が、こうしたいろいろな手法に関心を持つのは必ずしも悪い傾向ではないと思うが、どうもそうした動きを見ていると、何か「もっと」適切な手法さえあれば、もっと効率的に、もっと的確に分析ができるのではないか、という、いささか他力本願的な姿勢が垣間見えることがあり、そのあたりが気になっている。
定性的な手法として古典的なものにはGTA (Grounded Theory Approach)や、そのバリエーションとしてのMGTA (Modified GTA)があり、このためにはQDAソフトも市販されている。その他に大谷尚のSCAT (Steps for Coding and Theorization)、Gendlin & HendricksのTAE (Thinking at the Edge)などがあるが、もっと古典的なものとしては川喜田二郎のKJ法などもある。KJ法は僕も良く利用しているが、その理由はその発想がとても基本的 なもので不自然さや難解さがなく、素直に利用できるからだ。GTAについては何回か利用を試みたが、手続きが煩雑で、たしかに理論構築をするには 良いのかもしれないが、設計への示唆を得るという目的からするといささかオーバースペックに思える。SCATについては、分析にExcelを利用 するという点では僕のやっているやり方に近いが、それでもGTAに影響されていて手続きがいささか厳密に規定されているので、個人的にはあまり好まない。
ここでちょっと考えてみたいのは、エスノグラフィの先駆的研究者であるMalinowskiやLevi Straussのことだ。彼らは「偉大な」人類学者といわれているが、別に特定の分析手法を開発したり、それを利用したわけではない。あくまでも自身の直感と洞察にもとづいて理論構築をしてきた。僕はそれでいいのではないか、と思っている。
最近、総研大の比較文化学専攻のマリアヨトヴァが、経営人類学の分野で「ヨーグルトをめぐる言説の生成と展開-社会主義期からポスト社会主義期にかけてのブルガリアを中心に-」という大変すばらしい論文をまとめて学位を得ている。彼女が採用した手法は、質問紙とインタビューであるが、インタビューに関しては実に5年間に8回ものブルガリアでの調査を実施している。しかし彼女はGTAを使ったりしている訳では無い。あくまでも自身の洞察力を用いて理論構築をしている。もちろん理論構築と設計への応用を考える場合とは研究調査のスタンスは異なるが、データ分析の緻密さへの要求は理論構築では厳しい筈だが、反対に設計への応用においてはそれよりも軽いのではないだろうと思う。
振り返ってGTAが良く使われているのは質的心理学会関係者である、という点に注目すべきだろう。そもそも質的心理学は、実験心理学が幅をきかせている心理学会にあって、定性的アプローチが妥当な評価を得てこなかったことから、関係者が結束してできた学会である。心理学だけで無く看護学などの分野でも多用されているが、ようするに特定の分野におけるディシプリンが定性的なデータやその分析、そしてそれにもとづく提言を低く評価してきたような場合には、それに対する闘いのために理論武装をする必要があり、それがGTAという武器を得て力づけられた、という経緯がある。
さらにアナロジーとして振り返るべきことは、ユーザビリティテストにおけるプロトコル解析の位置づけである。初期のユーザビリティテストにおいては、その状況が心理学における問題解決場面に近いことから、そこで利用されていたプロトコル解析の手法を応用することが常道とされていた。しかし、プロトコル解析は、本来、人間の問題解決プロセスを分析するための手法であり、具体的な問題点を見つけることを目的とするユーザビリティテストからすると、いささかオーバースペックであった。さらに、ある機器利用場面における人間の認知モデルが明らかにされたとして、そのモデルが新しいデザインに結びつくかというとそうでもなかった。そうした理由で、プロトコル解析とユーザビリティテストの蜜月時代は終わりを告げ、現在では、問題点としてのエラーや逡巡を見つけ出すというダイレクトな作業が中心になっている。この経緯は、質的データ分析にとって示唆的であるし、また問題発見というユーザビリティテストの目的からすれば適切なやり方に定着してきたと考えている。
僕の言いたいことはここまでの論述で明らかになっていると思うが、ようするにいろいろな分析法を利用することは、時にマネージャや設計者、デザイナなどの関係者が頑迷な場合には理論武装として必要かもしれないが、そうした関係者が評価の意義を認めつつある現在においては、もう必要ないのではないか、ということである。もっと実効的なやり方によって活動していくべきではないか、ということである。
ただ、注意しなければならないのは、こうした質的分析にはある程度の熟練が必要である。初心者がいきなり直感と洞察に頼って何らかの主張を行うのは危険である。その意味で、ひととおりのお作法を学ぶという目的でこれらの分析手法を利用するのは教育的観点から好ましいことといえるだろう。また、自分の直感力や洞察力に自信のない場合にも、こうした手法の助けを得ることはいいことかもしれない。その意味では、こうした手法への依存傾向には一理あると考えてはいる。
余計なことかもしれないが、ユーザビリティ関係者やUX関係者の学会発表というものが、多くの場合「新手法」の開発になっていることについては、そんなに沢山の手法が必要なのか、そんなに手法に依存しなければやっていけないのか、という素朴な疑問を抱いている。手法を学ぶ場があると、すぐに予約が満席になることも、関係者が熱心に取り組もうとしているという熱気が伝わってくるという意味では好ましいのだが、もっと自分たちの「あたま」を使うようにすべきではないか、と思ってしまうのである。
(※2011年12月31日、記事内容を一部変更いたしました – 編集部)
記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。