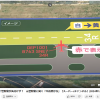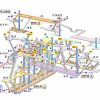歩行者のUXを高めるために - 自転車との関係
ちょっと前まで自転車の無法運転がまかり通っていた。しかし、2024年11月の改正道路交通法の施行以来、変な運転をする自転車利用者の数は大きく減ったように思われる。
横暴な無法自転車
ちょっと前までは、自転車の無法運転がまかり通っていた。歩道といわず車道といわず左右に振れて人や駐車中の車を追い抜き、スイスイと20km/hくらい、時にはそれ以上のスピードで走り回っていた。しかも左側通行も右側通行も関係なしに、道路が空いていればそこに突っ込んでくる。
車道を走っている自転車は、左側も右側も関係なしに走るから、時に同じ側で反対方向の自転車が向かい合ってしまうことがある。そうした時、不思議なことに違反者つまり右側を走ってきた自転車は歩道側のより安全な方にまわり、きちんと左側を走ってきた自転車が追いやられて大きく車道の側に膨れてしまうことになる。違反をしている自転車には自動車のやってくることが見えているから危険回避のために安全サイドに寄ろうとするのだろうが、正しい自転車にとってはたまらないことだ。
歩道での自転車の並走も良く見かけた。多くは中年のおばちゃん達であり、何かを喋りながら楽しそうに運転している。ご本人たちは楽しいのだろうが、狭い歩道で並走してこられると歩行者としては避けるために体をよじらなければならない。もちろんおばちゃん達はそんなことにはお構いなしだ。あと、車を運転しているときに車道の左側を走っていた自転車が急に車道の中に飛び出して、反対側に移動しようとすることもあった。後ろから自動車が来ているかを確認してからならまだしも、いきなり車道に振り出してくるのだ。事故がおきないようにするのは自動車の役目だ、と思っているかのようだ。
少し日時が経過するとスマホ問題がでてきた。スマホの画面を見ながら運転してくる。歩きスマホも問題になっていた時期だが、スピードのでている自転車では危険なことこの上ない。イヤホンをして音楽でも聴いているようなライダーもいた。人間の注意力の総量は有限だから、運転中は前方や周囲の視覚情報への注意と環境からくる音響に注意をむけるべきなのだが、音楽を聴きながら自転車を運転するというのは見ていて腹立たしかった。
駅前広場など、自転車は手押しで進んでくださいという呼びかけが書かれている場所での自転車の運転も結構目にしたものだ。調布駅の交番前の広場でも、警察官の前を堂々と運転している自転車があり、これまた見ていて不快になるものだった。
インフラ整備に関わる問題
運転ではないが、歩道にはみ出した駐輪もひどいものだった。整列して駐輪している自転車の間に自分の自転車を強引に割り込ませる者がいたり、ひどい場合には駐輪枠(駐輪している自転車の列)からはみ出し、通路側に駐輪していることもあった。違反駐輪自転車は自治体がトラックにのせて移動してしまう措置をとるようになったが、それでも一向に数は減らなかった。
もとはといえば公共駐輪場が少なかったことが原因なのだろうけれど、これは少しずつ、各自治体が公共駐輪場を整備するようになって、少しずつ解決しつつある。ただ、主に駅周辺に設置されることが多いのだが、駅から結構遠くに設置されている場合もあり、利用者の意向をきちんと汲む形にはなっていない。しかし、有料であってもこうした施設を利用とするユーザが増えてきたことは好ましいことと思う。
もうひとつ欧米、といっても自転車王国のオランダとか北欧あたりでしか見かけたことはないが、自転車専用レーンが日本では整備されていない、ということがある。図1はスウェーデンのウプサラで撮った写真だが、歩道とは別に自転車専用レーンが設置されていることがわかる。歩いていてうっかりここに立ち止まっていたりすると、自転車利用者に怒鳴られてしまうこともあるのだが、ともかくこれは自転車利用者にとっても歩行者にとっても安全が確保できる画期的な仕組みだとは思う。しかし、いかんせんスペースの問題がある。今の日本でこれを整備しようとしたら沿道の住宅を削るしかないだろう。最初から計画していなければ無理なことである。

2024.11.1に施行された改正道路交通法
以上に挙げたものには既に道路交通法に違反する行動も含まれていた。たとえば並走については、軽車両の並走の禁止として、「第19条 軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない」という条文が含まれており、即刻取り締まりの対象になってもおかしくないものだった。その他、右側通行など、既存の道路交通法で規定されていることは多く、いいかえれば、既に法律違反をしている自転車は多数あったということである。ただ、警察は自転車の交通違反については、事故でもおこさないかぎり大目にみていることが多かった。
しかし、2024年11月に改正道路交通法が施行され、またその運用が厳格化されたことによって事情は大分変化してきた。自転車の酒気帯び運転に対する罰則が新たに設置されたほか、自転車運転中の「ながらスマホ」も禁止されて罰則の対象となった。特に大きかったと筆者が考えるのは、自転車等に対する交通反則通報制度の新設、つまり青切符の導入が行われるようになったことである。この点については、どしどし違反を摘発して反則金を課してほしいと思っている。
ともかく、この改正道路交通法の施行以来、変な運転をする自転車利用者の数は大きく減ったように思われる。まあ、いまでは電動キックボードの暴走や、その無軌道な利用法が問題になったり、外国人への甘い免許交付のやり方などが問題になってきているが…。
自転車運転にも免許制度を
今回、結論的にいいたいのは、自転車にも免許制度を、ということである。これは当然無免許運転への罰則を伴うものであり、違反運転をしていなくても、免許証をもっていないだけで罰金を科し、違反をすれば最悪免許停止になるようにするのだ。こうすれば、自転車利用者は今以上に責任感をもって自転車を運転するようになるだろうし、自転車と共存している歩行者のUXも向上するだろうと考える。
記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。