リモートワークとグループウェア研究 1/2
COVID-19は、全世界の人々にこれまでの生活や業務の在り方の適否をあらためて問いかけることになった。人びとが自宅から外出できないという異常な状況が、遠隔教育や在宅勤務という問題についての早期の取り組みを促している。ここでは、在宅勤務にける事務作業に必須なリモートワークについて考えてみたい。
COVID-19による在宅勤務への社会的要請
COVID-19 (新型コロナウイルス感染症)は、全世界の人々にこれまでの生活や業務の在り方の適否をあらためて問いかけることになった。全世界が同じ問題を突き付けられたという意味では、これは人類史上初めてのことだといえる。しかもテレビというメディア技術やインターネットという情報技術のおかげで、世界全体が同じ脅威の認識を同時に持つことになったという点でも実に特異な状況といえる。
感染症医療という直近の問題もあるし、違反に対する罰則を含めた都市のロックダウンという政治的状況も、また世界経済の沈滞という中長期的な問題も重要だが、そのほかにも人びとが自宅から外出できないという異常な状況が、遠隔教育や在宅勤務という問題についての早期の取り組みを促している。ここでは、在宅勤務にける事務作業に必須なリモートワーク(テレワークともいう)について考えてみたい。なお、COVID-19の影響では、(通勤可能な場所に居住していながら)通勤をしない在宅勤務としてのリモートワークが注目されるようになったが、もともとはそれだけでなく、遠隔地にいて業務を行うことも含まれている。
リモートワークの必要性
COVID-19の感染を避けるために、オフィスのように「①換気の悪い密閉空間、②人が密集している、③近距離での会話や発声が行われる、という3つの条件が同時に重なる場」(3つの密)を回避する取組み(行動変容)を、より強く徹底して行うことが求められるようになり、企業においては在宅で業務を行うリモートワークが注目されることになった。
現在では、ノートパソコンの場合、マイク、スピーカ、ビデオカメラが標準装備されるようになっており、たとえばSkypeを使って打合わせをすることは、何年も前から(少なくとも対面打合わせを補完する位置づけとしては)一般化していた。もちろんデスクトップでもカメラとマイクとスピーカないしイアフォンを接続して、そのツールを使うことができる。そして音声だけで打合わせをすることもできる。最近は資料共有ができるZoomの利用が活発になっているようだが、それらは基本的にはシンプルな動画像通信(ないしは音声通信)のツールである。
業務というのは会議や対面の打合わせだけではないので、メールやファイル転送、ファイル共有、遠隔ログイン、ビジネスチャット(Slackなど)のようなツールも使いながら、文書作成や表計算などの仕事を行うことが含まれる。もちろん、業務によっては、製造業のライン業務のようにリモート化することが困難なものがあるので、業務形態や業務内容による検討は必要である。
グループウェアという研究領域
もう忘れられかけているかもしれないが、HCI (Human Computer Interaction)の領域で、1980年代後半から1990年代にかけて、CSCW (Computer Supported Cooperative Work)やグループウェア(groupware)という研究が活発に行われていた。当時はPCが普及し始めた時期であり、また大容量の高速通信が利用可能になった(といっても現在に比べればまだまだのレベルだったが)ことから、それを使ってパーソナルな業務環境を通信によって結合した業務支援環境を研究しようという考え方が生まれてきた時期だった。筆者も110インチの大画面表示装置と立体音響と大容量通信を使ったグループウェアの研究をやっていたことがある。そこで、当時の代表的な著作のひとつである『CSCWとグループウェア』(石井裕著、オーム社 1994)を読み返しながら、ちょっとその内容について批判的に説明することにしたい。
まずグループウェアについて、石井は「共通の仕事(または目的)をもって働くユーザグループを支援し、協同作業環境へのインタフェースを提供するコンピュータベースのシステム」というエリス達(1991)の定義を引用している。あたりまえのことを言っているように思えるが、パーソナル環境だけで仕事をしていた当時では、これだけでも何か新しいことができそうだという期待感をあおるものだったのだ。
1. 電子会議室
最初に試作されたのは、大画面ディスプレイと参加者の前に備えられた端末を組み合わせた対面会議の支援環境(図1のXerox PARCのColab (1987)やEDSのCaptureLab (1988)など)だった。これらは電子会議室とも呼ばれていた。
しかし、プロジェクタが普及した現在では、高額な大画面ディスプレイは利用せず、会議室壁面にイメージを投影する形が一般化しており、また参加者はたいていの場合、各自のパソコンをもって会議に参加し、HDMIケーブルを譲り合うことで、自分の画面を壁面に投影している。したがって、現在では図1に見られるようにデスクに固定されたコンピュータを使うのではなく、自分のパソコンを持って行き、自由に環境をセットアップするようになっている。結局のところ、このシンプルな構成が、学会において研究成果として発表された様々なグループウェアよりも使いやすいことがわかり、従来の会議形式の延長上にあるものとして普及したのである。
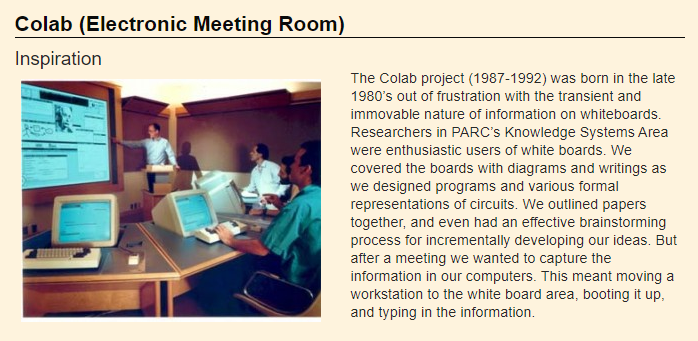
しかしながら、石井はこのような電子会議室を、プレゼンターから参加者への一方向のコミュニケーション支援に過ぎず、参加者全員による協同情報操作を支援していないため不十分なものであると批判している。石井の批判は、当時の技術者の思いを代表しており、世界におけるその後の研究も共同操作の支援に工夫したものが多くなった。たとえば複数のカーソルを同時に操作できるようにしたり、複数の参加者が原稿の書き込みや訂正を同時にできるようにしたりしたものがでてきた。
しかし、そうした発明は、会議やミーティングにおける情報の扱いについて誤解していたところがあったように思う。たしかに、共同声明文をまとめる場合のように、いろいろな人がいろいろな意見をバラバラと出してくるのこともあるが、そもそもそうした文書作成のケースはそれほど多くないし、座長役がきちんと制御すればいいの話である。気の付かないうちに、やたらなところで文章が書き加えられたり削除されたりしたのでは、首尾一貫性のある文章ができあがらなくなってしまう。
実際に使ってみれば使いにくさが感じられたり不具合がでてきてしまうようなものが、目新しさだけで学会成果として通ってしまうような状況があったのだ。さらにいえば、CSCWの研究は、協同作業(CW)をコンピュータで支援する(CS)といいながら、結局のところ、協同作業に関する社会科学的な調査や分析が不十分で、工学系の開発者の思い込みで突っ走ることになってしまったのである。
2. ビデオ会議システム
もうひとつの流れは、遠隔地の間での動画像通信を利用したビデオ会議システムであった。これには、図2のXerox PARCのMedia Space (1993)、トロント大学のCAVECAT (1991)、BellcoreのCRUISER (1988)などがあった。現在では、パソコンでSkypeやZoomを利用するようなことになるが、当時は、現在われわれが便利に使っているような仕組みだけでは単に遠隔地をつないだに過ぎなく、それだけでは「研究成果として話題にならない」という考え方があり、そこに偶然の出会いの機能を盛り込んだり、遠隔地間で建築家に共同のスケッチ作成を行わせたりする「工夫」が加味されるようになった。
さらに学会全体として「会話においては視線一致が重要だ」という強迫観念のような思い込みがあり、トロント大学のHydra (1992)のように、一人の参加者に一つの小型端末(カメラ、スクリーン、マイク、スピーカが入っている)を割り当て、その端末を想定された座席配置の順番に机上に配置することにより、相手に目を向けて話ができるようにするシステムも登場した。しかし、現在では、(相手の目を見て話しをする文化圏の欧米でも)視線一致はそれほど重要ではないと思われており、単に参加者の画像が画面に併置されていればそれで良しとするようになっている。さらに現実には画像を使わずに音声だけで会議に参加する人もいるくらいである。
要するに、「研究として面白い」発明は、研究の世界だけで称賛されるものであり、実際には単純に「つなぐ」だけで良かったのだ。

(「リモートワークとグループウェア研究 2/2」へつづく)



