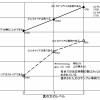ユーザビリティやUXに関係する4種類の心理学的「事実」(2)
探索型の心理学的「事実」
ユーザビリティ・UXと心理学とを関連づけた書籍が複数出版されている。そこに掲載されている心理学的「事実」とされるものには、幾つかのタイプがある。本稿では、そのうちの1つ、探索型について少し詳しく説明してみたい。
ユーザビリティやUXと心理学
前々回も書いたように、心理学的「事実」とされるものを筆者は4つに分類している。仮説検証型、探索型、経験則型、洞察型の4つである。ただし、これはあくまでも筆者の便宜的な分類であり、心理学の世界で一般的に用いられているものではない。
仮説検証型は、仮説をたてて実験や調査でそれを検証して「こうなんだよ!」というタイプ、探索型は、いろいろデータを集めて多変量解析なんかで調べてみたら「こうだったよ」というタイプ、経験則型は、我々が日常的に生活するなかで「こうなんだよね」ということを経験的にすでに知っているので確認できるタイプ、洞察型は、よくわからないことに関して「こうだと思うよ」という仮説的な構造を示したもので実験などによっては検証され得ないようなタイプである。
ユーザビリティやUXについて学んでいくと、心理学的「事実」や「法則」の類がいろいろと出てくるが、それぞれがどのような面で「科学的」なのかを踏まえた上で参照すべきだろう。
このシリーズではこの4つのタイプについて順に見ていくが、本稿では、探索型について少し詳しく説明してみたい。
人々の間に存在する個人差: 類型論と特性論
ユーザ、つまり人間の間に個人差があることは、別に心理学的な調査をするまでもなく、誰でもが知っていることである。ところで心理学のなかでも、性格心理学や価値態度心理学、知能心理学などには類型論と特性論という二通りの考え方がある。
類型論
類型論というのは、世の中には様々にちがった類型があり、この人はこの類型に該当する、あの人はこちらの類型に該当するというように分けてゆくもので、現在の心理学的にはその適切さについて疑念が呈されている。古代ギリシャのヒポクラテスや古代ローマのガレノスに由来する四気質説(気質を、黄胆汁質、黒胆汁質、多血質、粘液質に区別する)も類型論のひとつとみなすことができる。
また、クレッチマーの体格と性格(1931)という考え方がある。これは精神科医であった彼が、精神疾患の患者、そしてひいては一般の人々について、痩せ型は分裂気質、肥満型は躁鬱気質、筋肉型は粘着気質であることが多いと考え、体格から性格を類推しようとしたものである。これも類型論の一つとして有名である。
ただし、こうした理論構築のやり方から考えると、類型論は探索型には該当しないといっても良い。
特性論
その反対に、特性論の方は探索型に近いものが多い。特性論では、人間の性格にはすべての人々に共通して存在するいくつかの特性があると考える。そして個人差というのは、それぞれの特性の相対的な強さの違いの組み合わせによるものだ、という考え方である。
余談にはなるが、その意味では類型論は特性論の極端な場合と考えられなくもない。たとえば、すべての人に黄胆汁質、黒胆汁質、多血質、粘液質という特性が共通に存在しているが、黄胆汁質と特定される人は他の三種類の気質の値がゼロに近い場合である、というように考えるわけである。
HCDと性格特性
今回は、性格の問題を取り上げて、探索型のアプローチについて説明を加えたい。性格はさまざまな場面でHCDに関係している。たとえば、有名なロジャースのイノベータ理論だが、これは、新しいものに関心を示す度合い、いいかえれば新規性への接近的態度、もしくは好奇心の強さという形で性格が反映したものと考えられる。その意味では、イノベータ、アーリーアダプタ、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガードという5つの「タイプ」に分けられると解釈されることが多いが、これは類型論というよりは、むしろ好奇心の強さという特性に関するレベルの違いであり、類型論ではなく特性論の一つと考えるのが良いだろう。イノベータはその特性が最も強い人たち、ラガードというのは最も低い人たち、と考えるわけである。ちなみに、これは後述するビッグファイブの因子の1つである開放性に近い概念でもある。
また、緻密さや注意深さという特性は、仕事の環境における行動に関係しているため、プログラミングのような作業の場合には重要な特性だし、メールに添付ファイルをつけ忘れてしまうような行動にも関係する。メール本文に「添付」という言葉がありながらファイルを添付しないまま送信をしようとすると、アラートがでるような仕組み(たとえばThunderbird)は、そうした性格特性が引き起こす行動に対するHCD的な配慮といえる。
さらに、怒りっぽいという性格特性があって、ちょっとしたことで気に入らない人やものに対して怒り出すこと人がいる。こういう人がサービスデスクに電話をかけてきたときの対応の仕方などは、サービスに関するHCDによって対応すべきものである。
このように、性格はHCDの関係する様々な場面に関係してくるものであり、以下では特性論による性格の捉え方を、ちょっとその発展の歴史をまじえながら、その探索型的な性質を見ていくことにしたい。いささか心理学的な話が長くなるが、その点、ご了承をいただきたい。
特性論と探索型アプローチ
特性論の起源とされるのは、1936年に発表されたオールポートとオドバートの語彙研究とされている。彼らは、辞書を使って単語検索をして利用頻度の高い性格表現用語4504語を集め、表としてまとめた。つまり、この研究は探索的なアプローチということができる。彼らの研究ではまだ特性というグループにはまとめられていないものの、性格の特徴を表現用語のなかに求めようとする姿勢が基本的に含まれている。すなわち、我々が性格とみなす特性はすべて言葉として抽象化されているはずだ、という考え方が前提になっている。
この表に掲載されている言葉を特性として分類整理しようとしたのはキャッテル(1957, 1966)だった。彼は調査データをもとに相関係数行列をつくり、それに因子分析を適用し、12の因子を求めた。彼はそこに4因子をあとから追加し、合計16の性格因子を見出した。これが探索型としての特性論の出発点だったといえるだろう。キャッテルとは異なる考え方で、アイゼンク(1954)は内向vs外向、不安定vs安定という2つの次元を基本として2因子的な性格特性論を提唱した。いずれにしても、これは類型論ではなく、それぞれの因子で表現される性格特性がそれぞれどの程度対象となる人に見出されるかを考えようとしている点で特性論といえる。また、因子分析的な方法によって見つけられた特性をベースにして人間の性格を考えようとしている点で、探索的なアプローチということができる。
これらの研究では、探索型研究の結果、12の因子や2つの因子が見出されたのだが、その後の研究では、因子数が5つであるというFFM (Five Factor Model)が一般的に受け入れられるようになった。この考え方については、ゴールドバーグ(1981, 1990)が提唱したビッグファイブという呼び方も普及している。なお、FFMについて説明した資料を探っても、なぜ5つであり、4つでも6つでも、あるいはそれ以上でもないのか、という明確な説明は見つからなかったが、現在では、FFMがある意味当然のことのようにして受け入れられている。いずれにしても探索的な調査研究を行った結果、5つの相互に独立な性格特性が存在すると考える、というのが性格心理学の現状のひとつといえるだろう。
FFMについてはもう少し触れていくが、このように因子分析などの多変量解析手法を使って、調査した結果を分析し、そこに研究対象の構造を見出そうとするアプローチは、性格研究に限らず探索型の心理学的アプローチとして位置づけることができる。そこには「どのようになっているのか」という問いに対する答えはあるが、「なぜそうなっているのか」という問いへの答えはない。多変量解析の結果、こういう形が見出されたからです、というのが説明といえば説明になるだろう。多変量解析技術の進歩によって、要因間の因果関係を論じることができるようにはなったが、それはあくまでもモデルとしてリストアップされたことがらの間の関係であって、「根本的にこれこれだからこうなるのだ」といったように外部要因を導入して行う説明とは異なっている。あくまでもデータにもとづいて「経験的」に見出されたものから探索的に要因を見つけ出そうという形になっている。
ユーザビリティやUXの調査や研究でも、多変量解析を利用することは多くなっているが、基本的にそうしたアプローチが探索型の取り組みの結果であり、仮説検証型の取り組みとは基本的にちょっと違うんだ、ということは頭に入れておいたほうがいいだろう。ただし、仮説を検証するために多変量解析を使うこともあるから、多変量解析を使うと一概に探索型になってしまう、というわけではない。
FFMについてもう少し
5種類の性格特性を基本とするというFFMの考え方は、チュービスとクリスタル(1961)に始まる。その考え方を継いだコスタとマックレー(1987)は、その5種類の特性を計測するNEO-PI-Rという性格検査を提唱した。日本語訳はまだ定着していないが、柏木(1997)は、情緒不安定性、外向性、経験への開放、協調性、勤勉性という訳語を提案している。NEO-PI-Rでは、このそれぞれを更に6つの下位特性に分け、合計で30の特性によって性格を把握するような形になっている。この5特性については、杉山と堀毛(1999)が表1のようにまとめている。全く同一のものではないが、どれも概ね類似しているといえるだろう。
| Tupes & Christal (1961) | 高潮性 | 協調性 | 信頼性 | 情緒安定性 | 教養(文化) |
| Norman (1963) | 高潮性 | 協調性 | 誠実性 | 情緒安定性 | 教養(文化) |
| Costa & McCrae (1992)/下仲ほか(1998) | 外向性 | 調和性 | 誠実性 | 神経症傾向 | (経験への)開放性 |
| Peabody & Goldberg (1989) | 権力 | 愛情 | 仕事 | 感情 | 知性 |
| 和田 (1996) | 外向性 | 調和性 | 誠実性 | 情緒不安定性 | 開放性 |
| 辻ほか (1997) | 外向性 | 愛着性 | 統制性 | 情動性 | 遊戯性 |
さて、多変量解析、特に因子分析を使った研究では、因子数の推定という操作がある。これが探索型のアプローチとしての因子分析的研究の特徴のひとつでもある。ようするにデータの全体を説明するのにいくつの因子を想定すればいいのか、ということであり、前述した「なぜ5つであり、4つでも6つでも、あるいはそれ以上でもないのか」という点は、この操作に関係してくる。
もちろん因子数が増えればそれだけデータを説明する力は強くなるのだが、人間にとっては数の少ないほうが理解しやすく、そのあたりにトレードオフがある。それは短期記憶に関してミラー(1956)の提唱した7±2という説(マジックナンバー説)が、コーワン(2001)が提唱した4±1という説に置き換えられたことを引用するまでもなく、常識的にも10や20の因子数になると、全体の把握が困難になるという人間の認知的限界によるものでもある。
因子数の推定にはいくつかの方法があるが、一般に、第一因子、第二因子、第三因子…と処理をすすめていくと、その因子の負荷量は指数的に減少してきて、どこで因子の抽出をストップするかには若干の恣意性が入ってくる…というか、どのような因子数の推定法を用いるかについて恣意性が入りうると言ったほうがいいかもしれない。
そのようなわけで、探索的アプローチに多変量解析、特に因子分析を利用したような研究の成果には、切り捨てられてしまった因子もあるのだ、ということを考えておくことが大切である。もちろん、採択された因子をきちんと把握することがもっと大切なことではあるが。
探索型アプローチのまとめ
以上、説明してきたように、性格心理学の場合、現在は探索型アプローチにもとづいた特性論、とくにFFMがよく援用されるようになってきている。ただし、調べてみたらこうなったよ、という探索型アプローチであるが、最後の節で述べたように、『こうなった』という時の性格特性の数については、因子分析という手法の使い方が影響しており、素朴に「ああ、そうなんだ」と受け取ってしまう態度には気をつけなければならない。
心理学的事実を4つのタイプで区別しているこの連載であるが、心理学という経験科学における「事実」については、それなりの注意を払って、タイプごとの特徴を理解してその結果を受け止めることが大切だし、更にいえば、「だからインタフェースの設計においては、このようにしましょう」というガイドラインも素朴に鵜呑みにしてしまうのは危険である、ということにもなる。
「ユーザビリティやUXに関係する4種類の心理学的『事実』」目次
- 仮説検証型
- 探索型
記事で述べられている意見・見解は執筆者等のものであり、株式会社イードの公式な立場・方針を示すものではありません。