
寒くなると日本ではマスク姿の人が増えますが、アメリカではあまり見かけません。一方、日本では目上の人の前でサングラスをするのはマナー違反ですが、アメリカではそうは取られません。顔を隠す2つの手段、どうやら日米で心理的なギャップがあるようです。

日本心理学会の全国大会には「公募シンポジウム」という枠がある。今回は、「経験サンプリング法による心理学研究の新たな展開-スマートフォンを介して日常を探る」と「実学としての実験心理学6-応用と科学のジレンマを越えられるか」で考えたことを述べる。
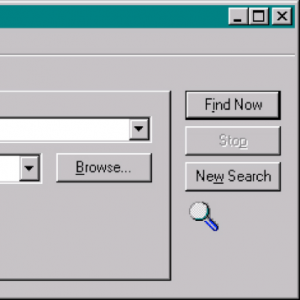
フラットデザインとは2012年ごろに広まったWebデザインのスタイルである。それは広く今も利用されているが、過度な利用は深刻なユーザビリティ上の問題を引き起こしかねない。フラットデザインによって発生するユーザビリティ上の最大の課題の1つに、クリック可能な要素のシグニファイア不足がある。フラットデザイン2.0は、それに対する優れた解決策を提供してくれる可能性がある。

日本心理学会の全国大会には「公募シンポジウム」という枠があり、勉強するにはとても良い機会だ。今年度、僕が指定討論者として参加した「衣食美心理学の可能性」の内容を紹介したい。僕自身は人工物進化学の観点から心理学に対して問題提起をした。

利用現場の状況に対する批判的アプローチにもとづいて手法を整備し活動を活性化してきた初期の世代と、それを継承し、より「楽しさ」や「うれしさ」、さらには「愛」を重視するようになった後の世代との間には、質的な変化が起きているのではないか。
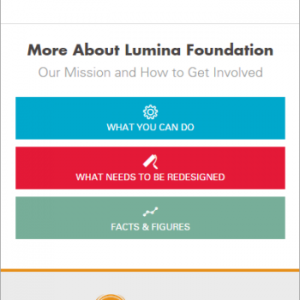
ハンバーガーメニュー(3本線メニュー)を利用しているモバイルサイトでは、移動を助けるサポートがサイト全体にわたって必要である。ユーザーがサイトのメインナビゲーションを見つけられなかったり、利用しないことがあるかもしれないからだ。

僕らの時期は、従来のコンピュータサイエンスの世界に対して反旗を翻し、新しいことを切実に考え出そうとした実験的な時代だったように思う。そして素直な性格の後の世代の研究者は、与えられた既存の方向性を素直に研究し発展させてきたのではないかと思う。

私が出会った東京旅行中の外国人旅行者の何人かは、これまでのように通常のホテルではなく、Airbnbという新しい選択肢を選び、民泊ならではの特別な体験を楽しんでいました。

人間中心設計推進機構(HCD-Net)は、産業界における人間中心設計へのニーズの高まりを背景に、今年度の「人間中心設計専門家(第7期)」および「人間中心設計スペシャリスト(第3期)」の認定試験を、11月25日(水)より受付開始いたします。

アメリカがカード社会であるというのは既知の事実ですが、Apple Payをはじめとした新しい決済方法(モバイルペイメント)の浸透具合はどうなのでしょうか。報道されていることと生活者の体感、日本の状況と比較しながら、リアルな姿をご紹介します。
ユーザビリティとは、製品・サービスのUIの、ユーザーにとってのわかりやすさ・操作しやすさの度合いのことです。
ユーティリティ(機能や性能)が高くても、使いにくいとユーザーが感じるようなものでは、その価値は下がってしまいます。
ユーザビリティの高いUIには、パターンやルールがあります。
ユーザー視点のフィードバックがユーザビリティを高めます。
UX(ユーザー体験、体験価値)とは、特定の製品・サービスの利用時・前後にユーザーの中で生じる知覚・反応のことです。
カスタマージャーニーマップ(CJM)は、ある目的を持つユーザーと特定の製品・サービスとのやりとりを視覚化したものです。
CJMの作成や分析には、必要な要素やコツがあります。
CJMを作成するには、UXを把握する調査が必要です。
ユーザビリティ評価も、UXを把握する調査も、その目的やタイミングによって適切な方法を選択する必要があります。